序論:史上最も長い待ち時間(使徒座空位、1268年~1271年)
1270年の夏、イタリア中部の都市ヴィテルボの教皇宮殿では、異様な光景が繰り広げられていました。かつてはキリスト教世界の君主として君臨した枢機卿たちが、大広間の床に間に合わせで張ったテントの下で身を寄せ合っていたのです。彼らの頭上には、壮麗な天井の代わりに、容赦なく照りつける太陽と、時折降り注ぐ冷たい雨を遮るものとてない、がらんとした空が広がっていました。ヴィテルボの市民たちが、業を煮やして宮殿の屋根を文字通り剥ぎ取ってしまったからです。この屈辱的な状況は、西欧キリスト教世界の最高権威が陥った深刻な麻痺状態を象徴していました。
1268年11月29日に教皇クレメンス4世が逝去して以来、教皇の座、すなわち「聖ペテロの座」は空位のままでした。後継者を選ぶための選挙は、1,006日間というカトリック教会の歴史上例のない長きにわたって続いたのです。この期間は単なる歴史上の珍事ではありません。それは、教会が自らを統治する能力を失い、キリスト教世界全体が指導者を欠いたまま漂流するという、深刻な統治危機でした。キリストの代理人を選ぶという神聖なはずのプロセスは、なぜこれほどの混乱に陥ったのか?どのような政治的勢力が、妥協不可能な膠着状態を生み出したのか?そして、この前代未聞の危機が、いかにしてカトリック教会で最も永続的かつ秘密主義的な伝統の一つである「コンクラーヴェ」―すなわち、鍵をかけて枢機卿を閉じ込める教皇選挙制度―を産み出すに至ったのか?探っていきます。
第1部:教皇のための王国―イタリアに差すアンジュー家の影
教皇庁の悪魔の取引
ヴィテルボでの膠着状態を理解するためには、13世紀のヨーロッパを支配していた巨大な権力闘争に遡る必要があります。それは、ローマ教皇を頂点とする教皇派(ゲルフ)と、神聖ローマ皇帝を支持する皇帝派(ギベリン)との間の、一世紀以上にわたる覇権争いでした。特に、南イタリアとシチリアを支配するホーエンシュタウフェン家の皇帝たちは、ローマを南北から挟み撃ちにする地政学的な脅威として、歴代教皇にとっての最大の懸案事項でした。
この長年の宿敵を根絶するため、教皇ウルバヌス4世とその跡を継いだクレメンス4世は、大胆かつ危険な賭けに出ました。彼らは、フランス王ルイ9世の野心的で冷酷な弟、シャルル・ダンジュー(アンジュー家のシャルル)に白羽の矢を立て、ホーエンシュタウフェン家討伐のための「教会の勇者」としてイタリアに招聘したのです。教皇庁はシャルルに対し、軍資金の援助を約束し、対ホーエンシュタウフェン戦を十字軍として宣言することで彼の遠征に正当性を与えました。
勇者にして脅威、シャルル・ダンジュー
シャルルの軍事行動は目覚ましい成功を収めました。1266年のベネヴェントの戦いでホーエンシュタウフェン家のマンフレーディ王を討ち取り、1268年のタリアコッツォの戦いでは、一族最後の男子である若きコンラディンを打ち破り処刑したのです。これにより、教皇庁の長年の脅威であったホーエンシュタウフェン家は完全に滅亡しました。その見返りとして、シャルルは教皇の封土であるナポリとシチリアの王位を授けられ、南イタリアにフランス系のアンジュー王朝を樹立しました。
しかし、この勝利は教皇庁にとって新たな、そしてより深刻な問題を生み出しました。古い敵を排除したことで、教皇庁は自ら招き入れた強力な「友人」の手に落ちてしまったのです。シャルルはイタリア半島において圧倒的な影響力を持つようになり、事実上、イタリア政治の裁定者となりました。教皇クレメンス4世の政策は、教皇庁の独立性を新たな脅威に晒す結果となったのです。この戦略的賭けが裏目に出たことの直接的な帰結が、ヴィテルボに集った枢機卿団の深刻な分裂でした。教皇選挙はもはや単なる教会内部の問題ではなく、ヨーロッパの新たな秩序をめぐる最初の主要な政治的戦場と化したのです。
分裂した枢機卿団
1268年11月29日にクレメンス4世がヴィテルボで亡くなると、後継者選挙のために枢機卿たちが同地に召集されました。しかし、彼らは一枚岩ではありませんでした。シャルル・ダンジューのイタリア支配を支持し、フランスの影響力を維持しようとするフランス人中心の「アンジュー派」(pars Caroli)と、この新たな外国勢力の支配に抵抗し、教皇庁の独立を守ろうとするイタリア人中心の「反アンジュー派」(pars Imperiiとも呼ばれた)とに枢機卿団は真っ二つに割れていたのです。
この選挙はもはや霊的な指導者を選ぶプロセスではなく、教皇庁がフランス王家の事実上の属国となるか、あるいは独立を保つかという地政学的闘争へと変わってしまっていました。枢機卿たちは聖霊の導きを求める祈りよりも、ヨーロッパの勢力図を描き直すための政治的計算に没頭していました。この根深く妥協の余地のない対立こそが、ヴィテルボの悲劇的な長期選挙の根本原因だったのです。
第2部:ヴィテルボの膠着状態(1268年~1269年)
君主たちの集い
選挙の初期段階は驚くほど悠長なものでした。クレメンス4世の死後、ヴィテルボの司教宮殿に集まったのは、総勢20名の枢機卿団のうち、不在の1名を除く19名でした。当時の慣習に従い、選挙は前教皇が死去した都市で行われることになっていました。最初の1年ほど、枢機卿たちの生活には切迫感がほとんど見られませんでした。彼らは1日に1度だけ投票のために集まり、それが終わるとヴィテルボ市内に構えた各自の快適な邸宅へと戻っていったのです。
こののんびりとしたペースの裏で、水面下の政治的駆け引きは熾烈を極めていました。教皇に選出されるためには、出席枢機卿の3分の2の票が必要でしたが、両派閥の勢力はほぼ拮抗しており、どちらの陣営も自派の候補者を当選させることも、相手方の候補者を阻止することもできませんでした。派閥の結束が固い限り、数学的に当選は不可能だったのです。
表1:分裂した枢機卿団 ― 1268年教皇選挙における主要派閥
| 派閥 | 主要な枢機卿 | 政治目標 |
| フランス・アンジュー派 (pars Caroli) | オットボーノ・フィエスキ、ギヨーム・ド・ブレイ、アンケロ・パンタレオン、シモン・ド・ブリー | フランス人、またはシャルル・ダンジューに好意的な人物を教皇に選出し、イタリアにおけるフランスの影響力を維持する。 |
| 帝国・イタリア派 (pars Imperii) | ジョン・オブ・トレド、シモーネ・パルティニエーリ、オッタヴィアーノ・ウバルディーニ、ジョヴァンニ・ガエターノ・オルシーニ、リッカルド・アンニバルディ | イタリア人、または非フランス人の教皇を選出し、アンジュー家の支配に抵抗して教皇領の独立を維持する。 |
教皇候補(パパビレ)と逃亡した聖人
数ヶ月が経過する中で、何人かの枢機卿が教皇候補(papabili)として名前が挙がりました。イングランド出身の碩学ジョン・オブ・トレドや、後に教皇ニコラウス3世となる有力貴族ジョヴァンニ・ガエターノ・オルシーニなどです。しかし、どの候補者も3分の2の支持を得るには至りませんでした。 選挙開始から2ヶ月が過ぎた頃、膠着状態を打開しようとするあまり奇妙なエピソードが生まれました。セルヴィタ会の総長であったフィリッポ・ベニーツィが、選挙の遅延を諌めるためにヴィテルボを訪れたのです。ところが、彼の高潔さに感銘を受けた枢機卿たちは、彼を妥協案の候補者として選出しようとしました。教皇になることを恐れたベニーツィは選出される危険を察知すると、密かにヴィテルボから逃亡し、事態が収まるまで身を隠したと伝えられています。この逸話は当時の枢機卿たちがいかに追い詰められていたか、そして政治的に分裂した状況下で教皇の座に就くことがいかに望ましくないものと見なされていたかを物語っています。彼らは解決策を見出すことに必死でしたが、派閥の論理から抜け出すことはできず、誰も火中の栗を拾おうとせず、時間だけが空しく過ぎていきました。
第3部:市民の焦燥―コンクラーヴェの発明(1269年~1271年)
ヴィテルボの不満
1年以上にわたる選挙の遅延はヴィテルボの市民たちの忍耐を限界にまで追い込んでいました。キリスト教世界全体が指導者を欠いているという宗教的な問題だけでなく、彼らにはもっと現実的な問題がのしかかっていたのです。枢機卿とその大規模な随行員たちの滞在費は、すべてヴィテルボ市が負担していたからです。終わりの見えない選挙は市の財政を圧迫し、市民の生活に直接的な影響を及ぼし始めていました。
市政長官による介入
ついに市民の怒りが爆発したとき、それは無秩序な暴動ではなく、市の行政当局による公式な行動として現れました。1269年末、市の指導者であったカピターノ・デル・ポポロ(市民隊長)のラニエーリ・ガッティと、ポデスタ(行政長官)のアルベルトゥス・デ・モンテボーノは、この異常事態を終結させるべく断固たる措置を取ることを決意したのです。彼らの行動は、教皇選挙の歴史を永遠に変えることになります。
強制措置の段階的強化
監禁(Cum Clave) 最初の措置は、枢機卿たちを物理的に隔離することでした。ガッティとモンテボーノは、枢機卿たちに教皇宮殿(パラッツォ・デイ・パーピ)から出ることを禁じ、扉に鍵をかけて閉じ込めました。彼らが新しい教皇を選出するまで、外部との接触は一切断たれたのです。この「鍵を以て」(ラテン語でcum clave)閉じ込めるという行為が、後に「コンクラーヴェ」という制度の語源となりました。
飢餓食 しかし、単なる監禁では頑なな枢機卿たちの意思を変えることはできませんでした。そこで1270年の夏、市政当局はさらに圧力を強めます。彼らは枢機卿たちへの食料供給を大幅に制限し、パンと水のみを与えることにしたのです。食事は外部との会話ができないよう、小さな窓を通して内部に渡されました。この過酷な食事制限は、後に教皇選挙の正式な規則の一部として取り入れられることになります。
屋根の剥奪(Palazzo Discoperto) 最も劇的でそして最も効果的だったのが最後の手段でした。飢餓作戦でも選挙が進まないことに業を煮やした市民たちは、ある種のブラックユーモアを込めて、宮殿の大広間の屋根を文字通り剥がし始めました。その目的は「聖霊が枢機卿たちの上に降りてくるのを助けるため」だと公言されたのです。この措置により、枢機卿たちは夏の灼熱の太陽や激しい雨風に直接晒されることになりました。1270年6月8日付で枢機卿たちが両市政長官に宛てた公式な抗議文が残っており、その中で彼らは自らが「屋根のない宮殿」(palazzo discoperto)に閉じ込められていると不満を述べています。考古学的な調査では、広間の床に杭を打ったような穴が見つかっており、これは彼らが雨風をしのぐために内部にテントを張って生活していた可能性を示唆しています。
この市民による物理的な強制措置は、単に選挙を早めるための圧力ではありませんでした。それは、枢機卿たちの意思決定の根拠そのものを変容させる力を持っていたのです。1年以上にわたり、彼らは快適な環境で派閥の勝利という政治的論理に基づいて行動していました。しかし、監禁、飢餓、そして風雨に晒されるという生命の危機に直面したことで、彼らの最優先事項は派閥の勝利から自己の生存へと劇的にシフトしました。この耐え難い苦痛が、旧来の選挙手続きを放棄し、後述する「妥協委員会」という全く新しい政治的革新を生み出す直接的かつ不可欠な触媒となったのです。この過酷な状況下で、枢機卿のうち3名が亡くなり、少なくとも1名(オスティア司教エンリコ・ダ・スーザ)は重病のために投票権を放棄して宮殿を去ることを余儀なくされました。もはや、現状維持は死を意味しました。変化は不可避だったのです。
第4部:妥協と十字軍士の教皇
6人委員会
2年9ヶ月に及ぶ苦行の末、ついに枢機卿たちの意思は砕かれました。1271年9月1日、生き残った枢機卿たちは、もはや通常の投票では決着がつかないことを認め、「妥協」による解決策を受け入れたのです。彼らは、選挙の全権を自分たちの中から選ばれた6名の委員からなる委員会に委任しました。この委員会には、おそらく主要派閥の代表者たちが含まれていました。記録によれば、シモーネ・パルティニエーリやジョヴァンニ・ガエターノ・オルシーニといった両派の重鎮が名を連ねていたとされます。
究極の部外者
驚くべきことに、この委員会は自分たちの仲間の中から教皇を選ぶことを断念しました。どの枢機卿を選んでも、派閥間の深い溝を埋めることは不可能だと判断したからです。代わりに彼らが下した決断は、前代未聞のものでした。彼らは、リエージュの助祭長であったテオバルド・ヴィスコンティを新教皇に選出したのです。この選択は二重の衝撃をもたらしました。第一に、ヴィスコンティは枢機卿ではありませんでした。第二に、彼は選挙が行われているヨーロッパにさえいなかったのです。 選挙当時、ヴィスコンティは聖地アッコ(現在のイスラエル)で、イングランドのエドワード王子(後の国王エドワード1世)と共に第九回十字軍に参加していました。彼は政治的に中立で、高潔な人物として知られており、分裂した枢機卿団をまとめることができる唯一の人物と見なされたのです。
聖ボナヴェントゥラの役割
この意外な妥協案の背後には、当時のフランシスコ会総長であった聖ボナヴェントゥラの存在があったとされます。市民による過激な介入を彼が扇動したという通俗的な話は、歴史的信憑性が低いものの、複数の資料が、彼が最終的な人選において重要な役割を果たしたことを示唆しています。ボナヴェントゥラは、その知性と徳望によって枢機卿たちから深く尊敬されており、妥協委員会に助言を与え、政治的に無色で尊敬を集めていたヴィスコンティの名を提案した可能性が高いのです。
玉座への長い道のり
ヴィスコンティが自らの選出を知ったのは、選挙から数ヶ月後のことでした。聖地で教皇選出の報せを受け取った彼は、イタリアへの長い帰途につきました。彼がヴィテルボに到着したのは、選出から5ヶ月後の1272年2月のことでした。さらに、彼は司祭ですらなかったため、正式に教皇として即位する前に、まず司祭に叙階され、次に司教に叙階される必要がありました。すべての儀式を経て、彼が教皇グレゴリウス10世として戴冠したのは、1272年3月27日のことでした。1,006日間にわたる教会の麻痺状態は、こうしてようやく終わりを告げたのです。
第5部:「危険あるところ」―ヴィテルボの永続的遺産
危機によって鍛えられた教皇
教皇グレゴリウス10世の治世は、彼自身の選出経験によって深く特徴づけられていました。3年近くにわたる教会の機能不全の末に選ばれた彼は、このような危険な空位期間(ラテン語で Ubi periculum、「危険あるところ」)が二度と繰り返されてはならないと固く決意していました。彼の最優先課題は、教皇選挙のプロセスを改革し、迅速かつ秩序ある後継者選出を保証する制度を確立することでした。
教皇勅書『ウビ・ペリクルム』(1274年)
その集大成が、1274年にリヨンで開催された第2リヨン公会議で発布された教皇勅書『ウビ・ペリクルム』です。この勅書は、教皇選挙(コンクラーヴェ)の規則を正式に定めたものであり、その内容はヴィテルボでの過酷な経験を色濃く反映していました。
厳格な隔離 枢機卿は教皇の死後10日以内に、教皇が死去した都市の宮殿に集まり、外界から完全に遮断された一つの共通の部屋に閉じ込められなければならないと定められました。これは、ヴィテルボで経験した監禁と、屋根のない大広間での強制的な共同生活を制度化したものです。
段階的な食料制限 選挙開始から3日経っても教皇が選出されない場合、枢機卿たちの食事は1日1品に制限されます。さらに5日が経過した場合はパンとワインと水のみに制限されます。これは、ヴィテルボ市民が枢機卿たちに課した兵糧攻めを正式な規則として採用したものでした。
政治からの隔離 この規則は枢機卿たちが外部と連絡を取ることや、あらゆる取引を行うことを固く禁じました。これは、シャルル・ダンジューのような世俗権力からの政治的干渉がヴィテルボの膠着状態を引き起こしたことへの反省から、選挙の霊的なプロセスを保護することを目的としていました。
近代コンクラーヴェの誕生
ヴィテルボの選挙は、近代コンクラーヴェが鍛え上げられたるつぼであったと言えるでしょう。焦燥した市民たちがその場しのぎで実行した過酷な措置が、教会法として採用され、洗練され、制度化されたのです。その後、時代と共に規則は修正され、最も厳しい食事制限などは緩和されましたが、グレゴリウス10世が確立した「秘密厳守、隔離、迅速な選出」という三つの基本原則は、今日の教皇選挙においてもその根幹を成し続けています。
今日、システィーナ礼拝堂で行われるコンクラーヴェは、教会の至高の権威、厳格な秘密主義、そして自律的な統治能力の象徴と見なされています。それは、教会が外部のいかなる力にも屈することなく、自らの指導者を決定する神聖な儀式です。しかし、この最も権威ある儀式が皮肉にも、教会がその権威を完全に失い、市民の力によって公然と屈辱を受け、外部からの支配に甘んじた歴史的瞬間にその起源を持つのです。ヴィテルボでの選挙は、枢機卿たちが地元の市政長官に支配され、公衆の面前で恥辱に耐えた、教会史上最も無力な出来事の一つでした。 『ウビ・ペリクルム』に定められた規則は、この屈辱的な経験を二度と繰り返さないための、一点一点が計算された防衛機制でした。秘密主義は公の晒しものにされたことへの反動であり、隔離は、市民の介入への反動であり、迅速さを求める圧力は、3年間の麻痺状態への反動です。したがって、コンクラーヴェは教会の生来の伝統から生まれたものではなく、その歴史的な脆弱性の記憶の上に築かれた制度なのです。その強固な手続きは、かつての深刻な弱さと外部からの支配に対する教会の制度的回答に他なりません。
結論:コンクラーヴェは市民の怒りが生み出した
1268年から1271年にかけての教皇選挙は、単なる歴史上の異常事態ではありませんでした。それは、ヨーロッパの政治地図が大きく塗り替わる中で生まれた教会史上、稀にみる危機であったのです。ホーエンシュタウフェン家という古い脅威を排除するためにフランスのアンジュー家を招き入れた教皇庁の政策が結果として自らの首を絞め、キリスト教世界の中心に深刻な権力の真空を生み出しました。 しかし、ヴィテルボで繰り広げられた混乱―激しい政治的対立、枢機卿たちの苦難、そして前代未聞の市民による介入―は、予期せぬ形で、カトリック教会で最も秩序正しく永続的な伝統の一つを生み出すための、きっかけとなりました。絶望的な状況下で市民が強いた過酷な措置が、グレゴリウス10世によって教会法へと昇華され、未来の教皇選挙のあり方を決定づけたのです。そして、それが映画にまでなった「コンクラーヴェ」の原型となったのでした。

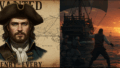

コメント