序論:闇夜に響く砲声、しかし敵はどこにもいなかった
1942年2月25日の夜明け前、アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスは、深い闇に包まれていました。突然、空襲警報の不気味なサイレンが鳴り響き、街の静けさを切り裂きます。夜空には何本ものサーチライトの光が交差し、第37沿岸砲兵旅団の対空砲が轟音を立てて火を噴き始めました。炸裂する砲弾の閃光が、恐怖におののく市民たちの顔を照らし出します。ロサンゼルスの上空で、後に「ロサンゼルスの戦い」と呼ばれることになる出来事が繰り広げられていたのです。しかし、この大規模な軍事行動の中心には、奇妙で不穏な矛盾がありました。砲火が向けられた先に、敵はいなかったのです。
この記事は「ロサンゼルスの戦い」が軍事的な交戦ではなく、当時のアメリカで高まっていた恐怖、人種的偏見、そして政府の混乱が燃え上がらせた「集団パニック」の、深刻かつ悲劇的な事例であったと論じます。空での戦いは架空のものでしたが、その地上での影響、特に日系アメリカ人に与えた結末は、破壊的で現実のものでした。
第1部 火薬庫寸前の西海岸:パニックを煽ったもの
1942年初頭のアメリカ西海岸の人々の心理状態は、いつ爆発してもおかしくない火薬庫のようでした。このパニックは根拠のないものではなく、現実の出来事と根深い偏見の土台の上に築かれていたのです。
1.1 真珠湾攻撃の衝撃:打ち砕かれた安全神話
1941年12月7日の真珠湾攻撃は、アメリカ国民が抱いていた「地理的に安全だ」という神話を根底から覆しました。攻撃以前、アメリカ政府は安全を強調していましたが、その信頼は完全に失墜しました。ハワイでは戒厳令が敷かれ、灯火管制や夜間外出禁止令が日常となり、市民生活は一変しました。このハワイでの厳しい現実は、やがて本土を覆うことになる恐怖の前触れだったのです。
真珠湾での壊滅的な軍事的・情報的な失敗は、戦前の「アメリカは難攻不落」という国家的な物語と真っ向から矛盾しました。その結果、政府がいくら「安全だ」と繰り返しても、奇襲攻撃の衝撃を経験した国民は、それを額面通りに受け取ることはできませんでした。国民の認識の枠組みは、「ここで起こるはずがない」から「それは現実に起こった、そして政府はそれを見抜けなかった」へと根本的に変化していました。この政府への信頼の欠如が、後に続く噂とパニックの温床となったのです。
1.2 目の前の敵:カリフォルニア沖での日本軍潜水艦の活動
西海岸の恐怖は、単なる妄想ではありませんでした。伊号潜水艦に代表される日本海軍の潜水艦は、実際に西海岸沖で活発に活動していたのです。1941年末から1942年初頭にかけて、これらの潜水艦は複数の商船を撃沈または損傷させていました。そして、その頂点となったのが、1942年2月23日、潜水艦「伊17」によるサンタバーバラ近郊のエルウッド石油製油所への砲撃事件です。
この砲撃による物理的損害は500ドル程度と軽微でしたが、その心理的影響は計り知れないものがありました。これは、1812年の米英戦争以来、実に130年ぶりにアメリカ本土が敵国から直接砲撃を受けた事件だったからです。夕暮れ時に浮上した「伊17」が沿岸の製油所に向けて17発から25発の砲弾を撃ち込む光景は、住民にパニックを引き起こしました。この単一の、しかし具体的な攻撃は、国民が抱く最悪の恐怖に現実の証拠を与えたのです。
「ロサンゼルスの戦い」は、このエルウッド砲撃事件と切り離しては理解できません。わずか1日前に発生したこの現実の攻撃こそが、西海岸全体の防衛システムと一般市民を極度の緊張状態に置き、過剰反応への引き金となる直接的なきっかけとなりました。実際に、海軍情報部は2月24日、「今後10時間以内に本土への攻撃が予想される」との警告を発しています。これはほぼ間違いなくエルウッド事件への反応でした。漠然とした侵略への恐怖は、具体的で差し迫った攻撃への予期へと変わったのです。誰もが亡霊を探していたからこそ、亡霊は現れた、と言えるでしょう。
1.3 「内にいる敵」:反日感情という負の遺産
第二次世界大戦以前から、日本からの移民とそのアメリカ生まれの子供たち(二世)は、1924年の移民法(通称:排日移民法)に代表されるような、制度的な人種差別に直面していました。真珠湾攻撃後、このくすぶっていた偏見は公然とした敵意へと燃え上がりました。日系アメリカ人は「敵性外国人」というレッテルを貼られたのです。当初、『ロサンゼルス・タイムズ』紙のように彼らの忠誠心を擁護する声も一部にはありましたが、そうした声はヒステリックな恐怖を煽る大波にかき消されていきました。
この根深い人種的敵意は、国民の恐怖と不安のはけ口として、都合の良い、目に見える標的を提供しました。日本軍による侵攻という抽象的な脅威は、日系アメリカ人コミュニティという具体的な存在に投影され、個人化されました。これにより、「侵略への恐怖が日系アメリカ人への疑念を煽り、日系アメリカ人への疑念が侵略の脅威をより現実的で陰湿なものに感じさせる」という危険な負の連鎖が生まれたのです。
その証拠に、「ロサンゼルスの戦い」の混乱の最中、約20名の日系人が「敵機に信号を送った」という容疑で逮捕されています。これは、攻撃が認識された瞬間、地域の日系人コミュニティが共謀しているという前提が自動的に働いたことを示しています。外部からの攻撃への恐怖と、内部の敵への疑念は、分かちがたく結びついていたのです。
第2部 最も長い夜:「ロサンゼルス大空襲」の1時間
このセクションでは、時間軸に沿って、あの夜の混沌と混乱の渦中へと読者を誘います。
2.1 最初の警報から本格的な空襲警報へ(2月24日 19:18 – 2月25日 02:25)
混乱の始まりは2月24日の夜でした。19時18分、防衛プラント付近で照明弾や点滅光が報告されたため、最初の警報が発令されましたが、これは22時23分に解除されました。本当の混沌は、2月25日の未明に始まりました。午前2時15分、対空砲部隊は「グリーン・アラート」(射撃準備完了)態勢に入ります。そして2時25分、ロサンゼルス郡全域に空襲警報のサイレンが鳴り響き、完全な灯火管制が命じられました。
2.2 空中戦の勃発(03:16 – 04:14)
午前3時16分、第37沿岸砲兵旅団が認識された目標に対して砲撃を開始しました。続く約1時間にわたり、彼らは約1,440発もの対空砲弾を夜空に撃ち込んだのです。目撃証言は著しく矛盾しており、1機から数百機に至るまでの飛行物体が、様々な速度と高度で飛行していたと報告されました。ラジオ局は、この「戦い」の様子を息をのむような実況中継で伝えたと言われています。
2.3 地上での混乱と犠牲
灯火管制の命令にもかかわらず、多くの住民は明かりをつけ、屋外に出て空の様子をうかがいました。空から降り注ぐ砲弾の破片は、建物や車両に被害を与えました。このパニックは5人の民間人の命を奪いました。3人は暗闇と混乱の中での交通事故で、2人は極度のストレスによる心臓発作で亡くなっています。
2.4 警報解除、そして謎だけが残る(07:21)
午前7時21分、ようやく警報解除のサイレンが鳴り響きました。夜が明けると、街には物的損害と5人の死、そして大きな謎が残されました。敵機は一機も撃墜されず、爆弾も一発も投下されず、そもそも敵機がそこにいたという証拠は何一つ見つからなかったのです。
表1:「ロサンゼルスの戦い」の時系列
| 日時 | 出来事 |
| 2月23日 夕刻 | 日本の潜水艦「伊17」がサンタバーバラ近郊のエルウッド石油製油所を砲撃。 |
| 2月24日 19:18 | ロサンゼルスで照明弾の報告により最初の空襲警報発令。 |
| 2月24日 22:23 | 最初の警報が解除される。 |
| 2月25日 02:15 | 対空砲部隊が「グリーン・アラート」(射撃準備完了)態勢に入る。 |
| 2月25日 02:25 | 郡全域に空襲警報発令。完全灯火管制が命じられる。 |
| 2月25日 03:16 | 第37沿岸砲兵旅団が認識された目標に対し砲撃を開始。 |
| 2月25日 03:16 – 04:14 | 約1,440発の対空砲弾が発射される。 |
| 2月25日 04:14 | 射撃停止命令。 |
| 2月25日 07:21 | 最終的な警報解除。 |
| 2月25日 午前 | 記者会見が始まり、矛盾する公式見解が発表される。 |
第3部 戦争の霧:矛盾、混乱、そしてメディア
このセクションでは、事件直後の状況を分析します。政府の不手際によって生じた情報の空白が、いかにしてメディアの扇情主義と憶測によって埋められ、この事件の神話的地位を確立したかを探ります。
3.1 二人の長官の異なる見解:崩壊する政府の発表
事件から数時間のうちに、政府の公式見解は分裂しました。フランク・ノックス海軍長官は記者会見を開き、事件全体を「不安と『戦争神経症』」に起因する「誤報」であると断じました。これとは対照的に、ヘンリー・スティムソン陸軍長官は、最大15機の未確認航空機が市上空を飛行したと主張し、それらは敵のエージェントが秘密飛行場から飛ばした民間機による「心理戦」の一環であった可能性を示唆しました。
この矛盾した声明は、単なる意見の相違ではありませんでした。それは、海軍と陸軍の間の根本的な対立と、それぞれの組織防衛の本能を反映していました。海上防衛を担当する海軍は、敵の空母や航空機をレーダーでも目視でも確認しておらず、国民のパニックを鎮静化させようとしました。一方、沿岸砲兵隊を管轄する陸軍は、膨大な量の弾薬を消費した後であり、無能で過剰反応したとの批判を避けるために自らの行動を正当化する必要がありました。スティムソンの声明は、憶測に基づいていたものの、陸軍の対応を是認する役割を果たしました。これは事実の表明というよりも、組織の威信を守るための行動だったと言えるでしょう。
表2:矛盾する公式見解
| 高官名 | 所属 | 声明・立場 |
| フランク・ノックス長官 | アメリカ海軍 | 事件は「神経過敏」による「誤報」であり、敵機の証拠はない。 |
| ヘンリー・スティムソン長官 | アメリカ陸軍 | 15機の未確認航空機が上空を飛行。敵による心理戦の可能性がある。 |
| ジョージ・マーシャル大将 | アメリカ陸軍参謀総長 | 敵エージェントがパニックを引き起こすために民間機を使用したというスティムソンの説を支持。 |
3.2 「ロサンゼルス上空で空中戦が激化」:メディアが恐怖を煽る
『ロサンゼルス・ヘラルド・エグザミナー』のような新聞は、「戦争号外」を発行し、「空中戦」が繰り広げられ、複数の敵機が撃墜されたと扇情的に報じました。『ロングビーチ・インディペンデント』紙は、「事件全体には不可解な沈黙があり、何らかの検閲が議論を止めようとしているようだ」と書き、政府による隠蔽工作を疑いました。このようなメディア環境は、メキシコ国内の秘密基地や沖合の日本軍空母といった荒唐無稽な憶測を煽る燃料となったのです。
3.3 千の説を生んだ一枚の写真
この事件の最も長く語り継がれる遺物は、1942年2月26日付の『ロサンゼルス・タイムズ』紙に掲載された一枚の写真です。この写真は、サーチライトの光線が明確な輪郭を持つ物体に集中しているように見えます。しかし、この写真は掲載前に大幅な修正(レタッチ)が加えられていました。これは当時、新聞印刷のコントラストを上げるために日常的に行われていた作業でした。
修正の少ない、あるいはオリジナルのネガを分析すると、この「物体」は、より拡散した雲のようなものであることがわかります。その正体は、サーチライトに照らされた対空砲弾の炸裂煙である可能性が極めて高いのです。この写真の修正は、おそらく悪意のある欺瞞ではなく、日常的な技術的判断でした。しかし、その結果は重大でした。それは、空中物体の存在を主張する最も過激な説を裏付けるかのような「証拠」を生み出してしまったのです。この一枚の操作された画像が何十年にもわたるUFO陰謀論の礎となり、信ぴょう性を生み出したのです。
第4部 謎の解体:気球、UFO、そしてその先
次に警報の引き金となったとされる様々な説を、最も確からしいものから最も思弁的なものまで、体系的に評価します。
4.1 公式説明:気象観測気球説
現在、最も有力な説は、1983年に空軍歴史局が結論付けたものです。それによれば、事件の引き金となったのは、午前1時に放たれた気象観測気球である可能性が高いというのです。米沿岸砲兵協会も、早くも1949年には同様の結論に達していました。一度砲撃が始まると、サーチライトに照らされた砲弾の炸裂煙そのものが、さらなる敵機と誤認され、誤った目撃情報の連鎖を引き起こしたと考えられています。ある報告では、サンタモニカ上空で赤い照明弾を付けた気球が目撃され、それが最初の砲撃のきっかけとなったと具体的に記されています。
4.2 現代の神話:UFO説
「ロサンゼルスの戦い」は、現在ではUFO研究の歴史における基礎的な出来事と見なされており、しばしば最初の大規模UFO事件として引用されます。この説は、前述の修正された『ロサンゼルス・タイムズ』の写真と、極度のストレス下では信頼性が著しく低いことが知られている目撃証言にほぼ全面的に依存しています。後年、地球外生命体の乗り物が回収されたと主張する「マーシャル/ルーズベルト・メモ」のような偽造文書も、この説を補強するために登場しました。
この事件は、極度のストレス下における人間の知覚の脆弱性を示す完璧なケーススタディとなっています。暗闇、死への恐怖、強力なサーチライト、そして炸裂する砲弾の組み合わせは、脳が感覚情報を正しく解釈することを困難にする環境を作り出しました。法心理学が示すように、人々は自らが予期し、恐れていたもの、すなわち敵機を見たのです。「侵略」という認知の枠組みが、気球や煙といった曖昧な刺激を、明確で差し迫った脅威へと変貌させたのです。
4.3 陰謀論的視点:心理戦
スティムソン陸軍長官自身の説は、敵のエージェントによる意図的な心理戦を示唆していました。また、この事件は、防衛産業を内陸部に移転させることを正当化するため、あるいは戦争への国民の支持を結束させるために、アメリカ当局によって画策されたものだという憶測もありました。しかし、これらの説を裏付ける信頼できる証拠は一切見つかっていません。戦後、日本政府は戦時中にロサンゼルス上空へ航空機を飛行させた事実はないと公式に確認しています。
第5部 真の犠牲者:誤報がもたらした人的コスト
最後にこの幻の空襲がもたらした最も重大な結果がアメリカ史上最悪の人権侵害の一つを加速させ、正当化する役割を果たしたことを説明していきます。
5.1 直接の犠牲者たち
まず、この事件によって間接的に命を落とした5人の民間人に敬意を表さなければなりません。3人は灯火管制下の交通事故で、2人は心臓発作で亡くなりました。この事実は、抽象的な歴史的事件を、具体的な人命の損失という現実に結びつけます。
5.2 不正義への触媒:大統領令9066号
フランクリン・ルーズベルト大統領は、「ロサンゼルスの戦い」の5日前にあたる1942年2月19日、大統領令9066号に署名していました。これは、軍が「あらゆる人物を排除」できる区域を指定する権限を与えるものでした。この命令自体は事件より先に存在しましたが、「ロサンゼルスの戦い」は、西海岸の日系アメリカ人がもたらすとされる脅威の、強烈で具体的な「証拠」を提供しました。これにより、人種に基づく大規模な収容に対する法的・道徳的な反対意見は押し流されたのです。
かつては市民の収容の合法性に懸念を示していたスティムソン陸軍長官でさえ、この認識された空襲の脅威と日系アメリカ人によるサボタージュの危険性を結びつけ、西海岸の軍事管理を強力に推進しました。その結果、アメリカ市民権を持つ者が3分の2を占める、11万人以上の日系人が、家や土地、事業を奪われ、戦争が終わるまで荒涼とした収容所に強制的に収監されました。彼らは財産だけでなく、基本的な人権をも失い、計り知れない精神的苦痛を味わったのです。
大統領令9066号は、法的に物議を醸すものであり、当初は一定の反対に直面していました。それは具体的な計画ではなく、広範な権限を与えるものでした。スティムソンのような推進派は、アメリカ市民を含む日系人に対してこの命令を適用することを、特に緊急の軍事的必要性として正当化する必要がありました。「ロサンゼルスの戦い」は、この政治的に絶好のタイミングで発生したのです。それは、大統領令が対処するために設計された「脅威」を、劇的かつ公然と可視化しました。スティムソンは即座にこれに飛びつき、「未確認機」を潜在的な敵エージェントと結びつけ、日系人は信頼できず、彼らの排除は緊急の軍事的要請であるという主張を補強しました。この幻の戦闘が日系アメリカ人への差別的な政策を推進するエネルギーとして利用されたといえます。
結論:目に見えない敵と実際に起きた悲劇
「ロサンゼルスの戦い」は、幻の敵との戦いであり、集団ヒステリーの典型例でした。真の敵は空にはおらず、地上に存在したのです。あの夜に発射された1,440発もの砲弾は、最終的には亡霊に向けられたものでした。しかし、その砲撃から生じた政治的影響は、現実の人々を標的としました。強制収容所に送られた日系アメリカ人こそが、決して起こらなかった戦いの真の、そして永続的な犠牲者なのです。

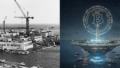

コメント