イギリスの古い街並みを歩いていると、時々、レンガで完全に埋められた、奇妙な「窓の跡」を見かけることがあります。まるでそこにかつて窓があったことを示す亡霊のようなこの痕跡は、一体何なのでしょうか?
実はこれ、かつてイギリスに155年間も存在した、世界でも類を見ない奇妙な税金「窓税(Window Tax)」が残した、生々しい歴史の傷跡なのです。
「光と空気に税金をかける」という、現代の私たちには信じがたいこの法律は、なぜ生まれ、人々の生活をどう変え、そしてどんな悲劇を招いたのでしょうか。今回は、イギリス史に刻まれた不思議な税金の謎に、専門家の声と共に詳しく迫ります。
なぜ「窓」に?奇妙な税金が生まれたワケ
窓税が導入されたのは1696年。当時のイギリス政府は、フランスとの戦争でお金が必要な上、硬貨の縁を削り取って貴金属を盗む「クリッピング」という不正が横行し、深刻な財政難にありました。
そこで、新しい税金として白羽の矢が立ったのが「窓」でした。 所得を直接調べる「所得税」は「プライバシーの侵害だ!」と国民の猛反発が必至でした。しかし、窓の数なら役人が家の中に入らなくても、外から数えるだけで済みます。
経済学の父として知られるアダム・スミスも、「窓は外部から数えられるため、査定はそれほど押しつけがましくない」と指摘しており、当時は比較的公平な方法だと考えられていました。ガラスがまだ高級品だったため、「窓が多い家=お金持ちの家」という理屈で、裕福な層から効率よく税金を集められる、画期的なアイデアだと思われたのです。
しかし、この一見合理的な発想が、後に国民を苦しめる悪法へと変貌していきます。
じわじわと国民を追い詰めた「税金地獄」
当初、窓税は「窓が10個以上の裕福な家」だけが対象でした。しかし、政府の財政は厳しくなる一方で、税のルールは年々改悪されていきます。
- 対象者の拡大: 課税の基準は、窓10個以上から7個以上へ、最終的には実質6個以上の家へと引き下げられ、ごく普通の中流家庭までもが課税対象となりました。
- 「窓」の解釈: 法律には「窓とは何か」という明確な定義がありませんでした。そのため、税務署員は自らの解釈で、壁の小さな通気孔や、食べ物の貯蔵庫の格子、ひどい時には**「壁のレンガが一つ外れただけの穴」**さえも「窓だ」と主張し、課税したのです。
- 税率の急騰: 決定打となったのが、1797年、時の首相ウィリアム・ピットが断行した窓税の3倍化です。これにより、国民の負担は限界を超え、イギリス全土で悲劇的な光景が見られるようになります。
「白昼の強盗だ!」レンガで窓を塞ぐ国民の抵抗
突如3倍になった重税から逃れるため、国民が取った最後の抵抗手段。それが、自らの家の窓をレンガで塞いでしまうという、悲しい選択でした。
光と空気を犠牲にしてでも、税金を払うまいとする人々。この光景はイギリス中で見られ、新しい家を建てる際にも、将来税金が廃止された時に備えて、窓のスペースをあらかじめレンガで埋めておくのが当たり前になりました。
この税は、自然の恵みである日光を奪う不当な税として、国民から「Daylight Robbery(白昼の強盗)」と呼ばれ、激しく憎まれました。この言葉は、今でも「法外な値段」「ぼったくり」を意味する慣用句として残っています。
最も苦しんだのは都市の貧しい人々
この税で最も深刻な打撃を受けたのは、裕福な人々ではなく、都市部の集合住宅に住む貧しい人々でした。 建物全体の窓の数で税額が決まるため、家主は税金を安くするために、容赦なくアパートの窓をレンガで塞いでいきました。その結果、貧しい借家人たちは、家賃を払いながら、光も風も入らない、暗く湿った不衛生な部屋での生活を強いられることになったのです。
闇が招いた病と医師たちの叫び
光と新鮮な空気が失われた住環境は、当然ながら人々の健康を蝕んでいきました。 当時、病気は腐敗物から発生する「悪い空気(ミアスマ)」を吸い込むことで伝染すると考えられていました。人々は外の「悪い空気」を恐れて窓を閉ざしましたが、皮肉にも、そのせいで室内のよどんだ空気が病原菌の温床となり、事態を悪化させたのです。
暗く、じめじめし、換気のない部屋では、チフス、コレラ、結核といった感染症が猛威をふるいました。
この悲惨な状況に、医療専門家たちが次々と警鐘を鳴らし始めます。
- ジョン・ヘイシャム医師の報告(1781年): 彼は、カーライルという街で発生したチフスの大流行を調査し、その発生源が、税金逃れのために窓が塞がれた一つの貧しい家に辿り着くことを突き止めました。彼はその家の空気を「圧倒的」と表現し、換気が全く機能していなかったと記録しています。これは、窓税が死を招いた具体的な証拠として、大きな衝撃を与えました。
- サンダーランド保健委員会の報告(1845年): 委員会は「窓税の非常に悪い影響と作用を目の当たりにした」と満場一致で報告し、窓を塞ぐことが病気を「大幅に悪化させた」と断定しました。
- 医療官たちの請願(1846年): ついに医療官たちは連名で議会に税の廃止を求める請願書を提出。「この税は、貧困層および社会全体の健康と福祉に最も有害である」と断言し、政治に決断を迫りました。
文豪チャールズ・ディケンズも「『空気のように自由』という言葉はもはや時代遅れになった」と述べ、この税がいかに非人道的であるかを痛烈に批判しました。
廃止への長い道と歴史の教訓
専門家や著名人、そして国民自身の声が高まり、窓税廃止の機運はかつてなく盛り上がります。1850年、議会で行われた廃止法案の採決は、わずか3票差で否決されるという大接戦となりました。
この僅差での敗北が、逆に改革派の最後の追い風となります。そしてついに1851年7月24日、導入から155年の時を経て、イギリス国民を苦しめ続けた悪名高き「窓税」は、歴史の舞台から姿を消したのです。
窓税の歴史は、私たちに多くのことを教えてくれます。良かれと思って作られた法律が、時に人々の生活を破壊し、命さえも脅かす「意図せざる結果」を招いてしまうこと。そして、当たり前のように享受している光や空気といったものが、いかに尊いものであるかということ。
イギリスの古い街角に佇む「塞がれた窓」は、単なる建築の跡ではありません。それは、非人道的な税に静かに抵抗した人々の記憶であり、歴史の過ちを二度と繰り返さないようにと、現代の私たちに静かに語りかける、歴史の証人なのです。


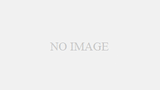
コメント