本州の山々では、クマの目撃情報が相次ぎ、その生息域は拡大しているとさえ言われています。 人里への出現も増えており、毎日のように熊の被害がニュースを報じられています。しかし、日本の主要な四島の中で、一つだけ、その「山の王」の気配が完全に消え去った島があります。それが、九州です。
なぜ、九州の森だけが、不気味なほど静まり返っているのでしょうか? かつて、この島の生態系の頂点に君臨していたツキノワグマは、一体どこへ消えてしまったのか。
そして、1987年、絶滅したと思われていた九州で、46年ぶりに一頭のクマが捕獲されます。それは、奇跡の生還だったのか、それとも…? 今回は、遺伝子解析という現代科学の光が照らし出した、九州のツキノワグマ絶滅を巡る、壮大で少しもの悲しいミステリーの真相に迫ります。
第1章:過去からの響き – 九州にクマがいた動かぬ証拠
この物語を理解するために、まず、私たちが向き合わなければならない事実があります。 それは、かつて九州には、間違いなくツキノワグマが生息していたということです。
石と土の中に眠る、骨の証言
2021年、この謎を解き明かす、決定的な証拠が発見されました。 熊本県球磨(くま)村にある「平田(ひらんた)の縦穴」という洞窟から、ツキノワグマの骨が発見されたのです。
この発見の持つ意味は、計り知れません。 放射性炭素年代測定により、この骨は7世紀から11世紀のものと特定されました。これは、遠い過去の化石ではなく、日本の歴史時代、すなわち奈良時代から平安時代にかけて、ツキノワgwinが九州の森を闊歩していたことを示す、直接的な証拠です。
そして、この発見場所の地名が「熊の村」を意味する「球磨村」であったことは、単なる偶然とは思えません。それは、かつてこの地域で、クマが人間にとって身近で重要な存在であり、その記憶が文化の中に深く刻み込まれていたことを示唆する、言語的な証拠でもあるのです。
人間が残した、畏敬の念
物理的な証拠に加え、人間が残した記録も、九州のクマの存在を物語っています。
- 熊塚(くまづか): 九州の一部地域では、クマは「イノシシ千頭、クマ一頭」と言われるほど、希少で強力な獲物と見なされていました。そのため、クマを仕留めた際には、その魂を慰めるために「熊塚」と呼ばれる石碑を建てる風習があったのです。
- 熊襲(くまそ): 『古事記』や『日本書紀』に登場する、古代の南九州に住んでいた人々の名「熊襲」。その名に「熊」の文字が含まれていることも、この動物が、かつてこの地のアイデンティティと深く結びついていた可能性を示唆しています。
これらの証拠は、九州のツキノワグマが、単なる一過性の来訪者ではなく、何千年にもわたって、この島の生態系に君臨していた「王」であったことを、私たちに雄弁に語りかけているのです。
第2章:絶滅への道 – なぜ「山の王」は消えたのか?
では、なぜ九州のクマだけが、姿を消してしまったのでしょうか。 その悲劇は、1万年以上も前に仕組まれた、地理的な運命と、近代以降の人間活動という、致命的な一撃の、二段階で進行しました。
後戻りできない「孤立」という運命
約1万年前、最終氷期が終わり、地球が温暖化する中で、海水面が上昇。それまで陸続きだった本州と九州は、「関門海峡」によって、完全に分断されました。 この瞬間、九州のツキノワグマは、本州の巨大な個体群から切り離された、典型的な「島嶼(とうしょ)個体群」となったのです。
ツキノワグマは泳ぎが巧みですが、関門海峡の速い潮流は、安定した遺伝的交流を阻む、あまりにも大きな壁でした。 外部から新しい血が入ることがなくなった九州のクマたちは、近親交配が進み、遺伝的な多様性を失い、病気や環境の変化に対して、極めて脆弱な状態に置かれることになったのです。
人間による「とどめの一撃」
この、長年にわたる孤立という脆弱性に、近代以降の人間活動が、致命的な打撃を与えました。
- 過剰な狩猟: 明治時代に入ると、狩猟の規制が緩和され、村田銃のような近代的な銃器が普及。日本全国で、野生動物に対する狩猟圧が劇的に増大しました。すでに小規模で孤立していた九州のクマたちが、この乱獲の時代を生き延びることが、極めて困難であったことは想像に難くありません。
- 食料庫の消滅: そして、とどめの一撃となったのが、戦後の「拡大造林」政策でした。 木材生産を目的としたこの政策により、クマの主要な食料源であるブナやナラといった、ドングリを実らせる広葉樹の森が、大規模に伐採されました。そして、その跡地には、スギやヒノキといった、クマにとっては食べ物のない針葉樹の人工林が、延々と植えられていったのです。
これは、クマにとって、食料庫と住処を、同時に奪われるに等しい行為でした。 食料を失い、断片化された狭い生息地に追いやられた九州のクマたちは、繁殖もままならず、「絶滅の渦」と呼ばれる、回復不可能な負のスパイラルへと、静かに飲み込まれていったのです。
第3章:「最後のクマ」のミステリー – 遺伝子が暴いた衝撃の真実
九州のクマの最後の確実な狩猟記録は、1941年。そして、最後の確実な生息の証拠は、1957年に発見された幼獣の死体でした。 その後、九州のクマは、完全に絶滅したと考えられていました。
しかし、1987年11月。 大分県の祖母・傾山系で、一頭のツキノワグマが捕獲されるという、衝撃的なニュースが日本中を駆け巡ります。
46年ぶりの発見。絶滅したはずの九州の個体群が、奇跡的に生き残っていたのか? 日本中の研究者と自然愛好家が、この「最後のクマ」に、一縷の望みを託しました。
しかし、この発見は、同時に激しい論争を巻き起こします。 捕獲された個体の歯が異常にすり減っていたことから、「これは、飼育されていた個体が逃げ出したものではないか?」という疑惑が呈されたのです。 このクマは、九州の希望の星なのか、それとも、ただの招かれざる客なのか。その謎は、20年以上にわたって、解明されることはありませんでした。
遺伝子が下した、最終審判
長年の論争に、ついに終止符を打ったのは、21世紀の科学技術でした。 2010年、森林総合研究所の研究チームが、保存されていたこのクマの体組織から、DNAを抽出し、その遺伝情報を解析したのです。
その結果は、決定的でした。
1987年に九州で捕獲されたクマは、九州在来の個体ではなく、本州の福井県から岐阜県西部にかけて生息する、東日本のグループに属する個体であった。
地理的に中国地方を飛び越えて、この東日本の遺伝子タイプが、九州に自然に存在することは、生物学的にありえません。 これは、このクマが、何者かによって本州から人為的に持ち込まれ、逃げ出したか、あるいは放たれた個体であることを、疑いの余地なく証明したのです。
この遺伝学的審判は、九州のクマの歴史を、根本から書き換えました。 1987年の「最後のクマ」は、希望の星ではなく、23年間、九州の生態史に存在し続けた「亡霊」だったのです。 そして、九州のクマの真の絶滅は、私たちが考えていたよりも30年も早く、1957年の幼獣の死体を最後に、すでに確定していたことが、明らかになったのです。
結論:沈黙の島からの警告 – 九州の森に隠された、もう一つの物語
九州のツキノワグマの物語は、一つの地域個体群の喪失に留まりません。 それは、同じく孤立した島嶼個体群である、四国のツキノワグマの未来を映し出す、恐ろしい鏡でもあります。
四国のクマの推定生息数は、わずか十数頭。もはや絶滅は時間の問題とされています。 私たちが今、四国で目の当たりにしているのは、かつて九州で、誰にも知られることなく静かに進行した、悲劇の最終幕の再演なのかもしれません。
現在、日本全国で熊の出現と人への被害が相次いでいますが、こうした九州に隠された熊の伝説と生態についても思いをはせてみてはどうでしょうか。

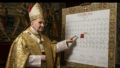

コメント