公の場で、思わず出てしまった「おなら」。多くの人にとって、それは顔から火が出るほど恥ずかしい、一刻も早く忘れたい失敗でしょう。
しかし、もし、その「おなら」を自由自在に操り、音楽を奏で、喝采を浴び、莫大な富を築いた人々がいたとしたら…?
これは、歴史の片隅に確かに存在した、世界で最も奇妙で、最も型破りな芸人「放屁師(ほうひし)」たちの物語です。 彼らは、なぜ最も卑俗なものを、人々を熱狂させる「芸術」へと昇華させることができたのでしょうか。今回は、古代ローマから現代のオーディション番組まで、時空を超えた「おならの達人」たちの不思議な系譜を追っていきましょう。
貴族が愛した「宮廷おなら芸人」
「おなら」を芸にすることが、単なる下品な悪ふざけではなかったことは、歴史が証明しています。 なんと、12世紀のイングランドには、王室お抱えの公式な放屁師が存在しました。
その名は、ローランド・ザ・ファーター(屁こきローランド)。 彼は、毎年クリスマスの日にヘンリー2世の前で「一つの跳躍、一つの口笛、そして一つの屁」を披露するという任務と引き換えに、広大な土地と邸宅を与えられていたという記録が残っています。
国家からその「才能」を認められ、土地まで授けられた芸人。彼の存在は、この奇妙な芸が、決して庶民だけのものではなかったことを示しています。
江戸のスーパースターと、彼を絶賛した天才学者
時代と場所は移り、18世紀の江戸。日本の大衆文化が花開いたこの時代にも、一人の伝説的な放屁師がいました。彼の名は、霧降花咲男(きりふりはなさきおとこ)。
彼の芸は、まさに名人芸でした。 お囃子に合わせておめでたい「三番叟の屁」を奏で、鶏の鳴き声を屁で模倣し、水車の音を鳴らしながら自分も回転する。そのパフォーマンスは江戸で大評判となり、連日、見世物小屋は満員御礼だったといいます。
この花咲男の芸に心底感銘を受け、一冊の本まで書き上げたのが、かの有名な天才学者であり発明家の平賀源内です。 彼は、著書『放屁論』の中で、花咲男の芸を詳細に記録し、こう絶賛しています。
「世の中には、高貴な思想や美しい歌声で金を得る者は多い。しかし、この男は、誰もが汚いと見捨ててきた『屁』を粗末にせず、工夫と修行の限りを尽くして見事な芸とし、金を稼いでいる。なんと立派なことではないか!」
源内は、花咲男の「卑しい」芸の中に、既存の価値観を打ち破る「創造性」を見出し、それを称賛することで、硬直した当時の身分制社会を痛烈に批判したのです。
ムーラン・ルージュを熱狂させた伝説の男「ル・ペトマーヌ」
この奇妙な芸の歴史において、おそらく最も世界的な名声を得たのが、19世紀末のフランスで活躍したジョゼフ・ピュジョール、通称「ル・ペトマーヌ(屁のマニア)」です。
彼の主戦場は、なんとパリで最も華やかなキャバレー「ムーラン・ルージュ」。毎夜、着飾った紳士淑女が集うこの場所で、彼は燕尾服を身にまとい、真面目な顔で舞台に立ちました。そして、驚くべきパフォーマンスを繰り広げたのです。
彼の最大の特徴は、消化ガスに頼るのではなく、肛門から自在に空気を吸い込み、それを放出するという驚異的なテクニックでした。これにより、彼は多彩な芸を可能にしました。
- 音楽演奏: 屁の音だけで「オー・ソレ・ミオ」やフランス国歌「ラ・マルセイエーズ」を演奏。
- 音の物真似: 大砲の音、雷鳴、動物の鳴き声などを完璧に再現。
- 蝋燭消し: 数メートル離れた場所にある蝋燭の火を、屁の風圧だけで吹き消す。
彼のショーは大成功を収め、ムーラン・ルージュで最も稼ぐスターの一人となりました。その収入は、当時の大女優サラ・ベルナールの2倍にもなったと言われています。卑俗な芸を、洗練されたスタイルと圧倒的な技術で見せる。そのギャップこそが、ベル・エポック期のパリの観客を熱狂させたのです。
現代に生きる「曲屁」の達人たち
この奇想天外な芸の系譜は、現代にも受け継がれています。
イギリスのミスター・メタンは、ル・ペトマーヌの後継者として、屁で音楽を演奏するパフォーマンスで知られています。 そして近年、世界的な注目を集めたのが、日本のお笑い芸人、市川こいくちです。
彼は、イギリスの人気オーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』に出演。「おならでろうそくの火を消す」「おならで矢を吹き、風船を割る」といった神業を披露し、審査員と観客を爆笑の渦に巻き込みました。彼のパフォーマンスはSNSで拡散され、国境を越えて多くの人々に知られることになりました。
テレビやインターネットという新しいメディアは、かつて見世物小屋やキャバレーで披露されていたこのアンダーグラウンドな芸に、新たな活躍の場を与えたのです。
【謎の真相】その驚くべきテクニックと文化背景
では、彼らは一体どうやって、このような神業を可能にしているのでしょうか? その謎の核心は、ル・ペトマーヌも使ったとされる「空気の吸入・排出」テクニックにあると言われています。彼らは、消化の過程で生まれるガスに頼るのではなく、まるで呼吸をするかのように、肛門から意図的に空気を体内に吸い込み、それを括約筋の絶妙なコントロールによって排出しながら、多彩な音を生み出しているのです。それは、彼らの体が一種の「楽器」と化している状態と言えるでしょう。
「屁負比丘尼」という奇妙な職業
江戸時代の日本には、この芸の背景にある、おならに対する人々の複雑な感情を象徴する、もう一つの奇妙な職業がありました。それが「屁負比丘尼(へおいびくに)」です。
これは、高貴な身分の女性に仕え、もし主人が人前でおならをしてしまった際に、「今のは、私がいたしました」と瞬時に名乗り出て、主人の恥をすべて肩代わりするという仕事です。 当時の上流社会では、女性が人前でおならをすることは、人生を左右するほどの恥とされていました。この「身代わり」という職業が存在したこと自体が、おならという行為がいかに社会的に抑圧されていたかを示しています。
このような強烈なタブーがあったからこそ、それを公然と、しかも芸術的に披露する「放屁師」の存在は、人々に驚きと、一種の解放感をもたらしたのかもしれません。
結論:歴史のファイルに刻まれた、芳しくも記憶に残る遺産
放屁師の歴史は、人間の身体が持つ無限の可能性と、文化の多様性を教えてくれます。 それは、最も「俗」なるものを、卓越した技術と創造性によって「芸」へと昇華させる、驚くべき錬金術の物語です。
平賀源内が花咲男を称賛し、パリの紳士淑女がル・ペトマーヌに熱狂したように、人々はその奇妙な芸の中に、既存の価値観を打ち破る痛快さや、人間の身体への尽きない好奇心を見出してきたのでしょう。

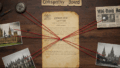

コメント