歴史上、最も心温まる戦争の話をご存知でしょうか?
1866年、小国リヒテンシュタインは80名の兵士を戦争に派遣しました。しかし、彼らは一人の犠牲者も出すことなく、それどころか「友人」を一人作って81名で帰還した――。
この、まるで民話のような逸話は、インターネットを通じて世界中に広まり、リヒテンシュタインの平和なイメージを象徴する物語として愛されています。
しかし、この伝説の裏には、大国同士の覇権争いに翻弄される小国の、存亡をかけた巧みな外交術と、知られざる歴史の真実が隠されていました。
この記事では、事実とフィクションを切り分け、この「世界で最も平和な戦争」が、いかにして現代リヒテンシュタインの礎を築く神話となったのか、その謎を解き明かしていきます。
公爵のジレンマ:大国の戦争に揺れる小国
この物語の舞台は、ドイツ統一の主導権を巡り、プロイセンとオーストリアが激突した普墺戦争(ふおうせんそう)の真っ只中、1866年です。
地政学的な板挟み
当時、リヒテンシュタインはオーストリアが主導するドイツ連邦の一員であり、有事の際には軍隊を派遣する義務を負っていました。オーストリアとの強固な同盟関係にあったリヒテンシュタインにとって、オーストリア側での参戦は避けられない選択でした。
しかし、この決定は国内で「我々は売られた!」という叫びが上がるほど、猛烈な反発を招きます。国民にとって、これは遠い大国の都合でしかない迷惑な戦争だったのです。
巧みな外交的妥協
この危機的状況で、若き君主ヨハン2世は驚くべき政治手腕を発揮します。彼は、国民感情に配慮して「同じドイツ人であるプロイセン兵とは戦わない」と宣言。その上で、オーストリアへの義務を果たすため、軍の任務をプロイセンの同盟国であったイタリアからの「チロル地方の防衛」に限定するという、見事な代替案を提示したのです。
これにより、リヒテンシュタインは最も熾烈な主戦場から遠ざかり、国民が嫌う「ドイツ人同士の戦い」を回避。さらにヨハン2世は、派兵にかかる費用を自らの私財から支出することを約束し、国民の不満を和らげました。この巧みな外交術が、後の「平和な戦争」を運命づけたのです。
アルプスへの行進:最後の軍事動員
こうして、リヒテンシュタイン史上、最後の軍事動員が開始されました。
派遣されたのは80名の兵士からなる部隊。指揮を執ったのは、リヒテンシュタイン出身のペーター・ラインベルガー中尉でした。
彼らに与えられた任務は、イタリアとの国境地帯、アルプス山中のステルヴィオ峠の防衛。兵士たちは険しい山々を徒歩で越え、高地の寒さや雪に見舞われるという過酷な行軍の末、任地に到着しました。
ワインとパイプの戦争?ステルヴィオ峠の平穏な日々
ステルヴィオ峠に到着したリヒテンシュタイン部隊ですが、その任務は驚くほど平穏なものでした。
約6週間の滞在中、彼らは一度も戦闘を経験せず、敵兵の姿を見ることすらなかったとされています。この平穏な任務から、伝説を彩る有名な逸話が生まれました。
兵士たちは美しい山々を眺めながら座り、ワインやビールを飲み、パイプをふかしてのんびり過ごしていた。
この逸話がどこまで真実かは定かではありませんが、彼らが戦闘とは無縁の時間を過ごしたことは確かです。その頃、主戦場ではオーストリア軍がプロイセン軍の前に壊滅的な敗北を喫していました。リヒテンシュタイン部隊の幸運は、ヨハン2世公爵の政治判断がもたらした、意図された結果だったのです。
戦争はわずか7週間で終結。部隊は一人の犠牲者も出さずに故郷へ帰還し、国中から盛大な歓迎を受けました。
伝説の81人目の兵士:友か、それとも役人か?
この物語の中で最も有名なのが、「81人目の兵士」の伝説です。80名で出兵したのに、なぜか81名で帰ってきたというこの話の真相は何だったのでしょうか。
- 説A:イタリア人の友人・脱走兵説 最もロマンチックな説。任務中にイタリア兵と友人になり、一緒に帰国したというもの。
- 説B:オーストリア兵説 リヒテンシュタインで仕事を探していたオーストリア兵が加わったという、より現実的な説。
- 説C:オーストリア軍の連絡将校説 そして、これが歴史的に最も信憑性が高いとされる説です。増えた一人は、部隊に随行していたオーストリア軍の連絡将校であり、帰還の際に護衛として同行した人物だったというものです。
歴史家ペーター・ガイガー博士の研究によれば、この81人目の人物は「連絡係として部隊に同行したオーストリアの将校」であったと結論づけられています。心温まる伝説の核心は、敵兵との友情ではなく、同盟軍内での極めて事務的な手続きにあったのです。
巧妙な平和:軍隊解体と永世中立への道
普墺戦争の終結後、リヒテンシュタインは歴史的な決断を下します。
1866年にドイツ連邦が解体されると、軍隊を維持する最大の理由が消滅。国民の強い要望もあり、1868年、リヒテンシュタインは軍隊の完全な解体を決定します。
そして、軍隊の廃止と時を同じくして永世中立を宣言。軍事力に頼らず、外交と国際法によって国家の安全を保障するという、小国ならではの生存戦略を選択したのです。この決断が、二つの世界大戦を乗り越え、現代に至る平和国家リヒテンシュタインの礎となりました。
リヒテンシュタインはどうやって軍隊無しで二度の世界大戦を生き延びた?
軍隊を廃止して永久中世国を宣言したからといっても、現実には大国、特にドイツからの侵略はリヒテンシュタインにとって、常に目の前にある恐怖でした。それを乗り越えて、永久中世国として生き延びりことができたのはリヒテンシュタインの巧みな戦略にありました。
結論から言うと、その最大の要因は「隣国スイスとの徹底的な一体化」です。軍事力を放棄したリヒテンシュタインは、スイスを事実上の「盾」とすることで、自国の安全を保障しました。
以下に、具体的な要因を解説します。
1. 保護者としてのスイス:外交・経済・防衛の全面的な連携
第一次世界大戦で、それまで緊密だったオーストリア=ハンガリー帝国が敗戦・解体し、リヒテンシュタインは国家存亡の危機に陥りました。ここで彼らが取った戦略が、オーストリアから離れ、同じく永世中立国であるスイスへ全面的に舵を切ることでした。
- 関税同盟の締結 (1923年): スイスとの国境を開放し、一つの経済圏を形成。これにより、リヒテンシュタインはスイスの広大な経済市場へのアクセスを得ました。
- スイスフランの導入 (1924年): 通貨をスイスフランに統一し、経済的な安定を確保しました。
- 外交の委任: 海外における外交代表権をスイスに委ねました。つまり、他国から見れば「リヒテンシュタインの利益はスイスの利益」と見なされる状況を作り出しました。
これにより、特に第二次世界大戦中、「リヒテンシュタインへの侵攻は、武装中立を掲げる強固なスイス軍を敵に回すことと同義である」とナチス・ドイツに認識させることができ、これが最も強力な抑止力となりました。
2. ナチス・ドイツにとっての戦略的価値の低さ
ナチス・ドイツにとって、リヒテンシュタインはいくつかの理由から、武力で併合・侵攻するほどの価値が見出せない土地でした。
- 地理的要因: スイスと、ドイツが併合したオーストリアに挟まれた山間の小国であり、軍事的な要衝ではありませんでした。
- 天然資源の欠如: 戦争遂行に不可欠な石油や鉄鉱石などの天然資源もありませんでした。
- 侵攻のリスク: 上述の通り、スイスとの深刻な対立を招くリスクを冒してまで手に入れるメリットがありませんでした。
3. 巧みな外交と国内の結束
第二次世界大戦前夜、リヒテンシュタイン国内にもナチスに共鳴する勢力「リヒテンシュタイン・ドイツ国民運動(VDBL)」が台頭し、1939年にはクーデター未遂事件も発生しました。しかし、当時の元首フランツ・ヨーゼフ2世は、巧みな政治手腕でこれを乗り越えます。
- 元首の国内常住: それまでウィーンに住んでいた侯爵家の当主として初めて、リヒテンシュタイン国内に居を構え、国民と共にある姿勢を示し、国民の結束を促しました。
- 連立政権の樹立: 国内の対立を避けるため、主要な二大政党による連立政権を維持し、ナチス勢力が国内政治を揺るがすのを防ぎました。
4. 金融センターとしての価値(タックスヘイブン)
これは第二次世界大戦後により顕著になりますが、リヒテンシュタインは厳格な銀行秘密法を敷く金融センターとしての地位を確立していました。ナチス・ドイツ関係者を含む各国の富裕層が資産を預けていたとされ、ドイツにとって、その金融機能を維持させることの方が、占領するよりも経済的な利益があったという側面も指摘されています。
結論:伝説が象徴するもの
「80人で出兵し、81人で帰還した」という伝説は、文字通りの事実ではありませんでした。しかし、この物語は、リヒテンシュタインという国が、大国の争いの中でいかにして自国の平和を守り抜き、非武装中立という独自の道を歩み始めたかという、歴史の転換点を完璧に象徴しています。
リヒテンシュタインが最後の戦争から持ち帰った最も価値あるものは、81人目の兵士ではなく、軍事力に頼らず、知恵と外交で平和を築くという国家のアイデンティティだったのです。この心温まる伝説は、これからもリヒテンシュタインという国のユニークな成り立ちを伝える、最高の物語として語り継がれていくことでしょう。

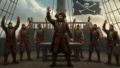

コメント