1932年、オーストラリアの大地で、歴史上最も奇妙な「戦争」が勃発しました。対峙したのは、最新の機関銃で武装したオーストラリア軍と、巨大な鳥・エミューの大群。
にわかには信じがたいですが、これはオーストラリア政府が公式に「宣戦布告」した、紛れもない史実です。
兵士たちはなぜ、鳥を相手に銃を構えることになったのか? そして、なぜこの戦いは「人類の敗北」として語り継がれることになったのか?
一見すると滑稽なこの物語は、当時の深刻な社会問題、人間と自然の複雑な関係、そして驚くほど深い教訓を秘めています。この記事では、世界史に燦然(さんぜん)と輝く珍事件、「エミュー戦争」の全貌に迫ります。
「敵」の正体:オーストラリアの象徴、エミューとは 🐦
この奇妙な戦争を理解するには、まず「敵」とされたエミューについて知る必要があります。
飛べない巨鳥の驚異的な能力
エミューは、ダチョウに次いで世界で2番目に大きな鳥。体高は最大2メートル、体重は60キロにも達します2。飛ぶことはできませんが、その代わりに時速50kmものスピードで疾走し、泳ぎも得意という驚異的な身体能力を持っています。
雑食性で、繁殖期を終えると水を求めて数千羽の群れで大移動する習性があります5。この季節的な大移動が、後に人間との大規模な衝突を引き起こす直接的な原因となりました。
神の鳥か、害獣か?人間との関係史
ヨーロッパ人が入植する以前、先住民アボリジニにとってエミューは、食料や薬(エミューオイル)としてだけでなく、神話にも登場する「神の鳥」として敬意の対象でした。彼らは自然と調和し、生態系のバランスを考慮しながらエミューと共存していたのです。
しかし、後の入植者たちはエミューを単なる「害獣」と見なしました。この価値観の根本的な違いこそが、エミュー戦争の遠い、しかし確かな火種となったのです。
なぜ戦争は起きたのか?大恐慌と農民の絶望
エミュー戦争の背景には、単にエミューが増えたというだけでなく、世界中を巻き込んだ深刻な社会的・経済的要因がありました。
世界恐慌の打撃と追い詰められた農民
1929年に始まった世界恐慌の波は、オーストラリア経済にも壊滅的な打撃を与えました。特に、小麦の輸出に依存していた農家は、価格暴落により収入が激減。多くは第一次世界大戦からの帰還兵で、政府の奨励政策で未開の地を開拓しましたが、その生活はすでに破綻寸前でした。
エミューの「侵略」と最後の嘆願
まさにその追い打ちをかけるように、1932年、約2万羽ともいわれるエミューの大群が、水を求めて農耕地へと大挙して押し寄せます。彼らは収穫間近の小麦を食い荒らし、畑を踏み荒らし、ウサギの侵入を防ぐための柵まで破壊しました。
生活の糧を根こそぎ奪われ、絶望の淵に立たされた農民たち(多くは元軍人)は、政府にこう嘆願します。「機関銃でエミューを駆逐してほしい」と。
機関銃 VS エミュー:滑稽で壮絶な戦いの記録
農民たちの悲痛な叫びを受け、オーストラリア政府は前代未聞の決断を下します。国防大臣ジョージ・ピアース卿の号令のもと、動物相手になんと正規軍が投入されることになったのです。
第一次作戦:エミューの奇策と軍の苦戦
1932年11月2日、「エミュー戦争」の火蓋が切られました。指揮を執るのはG.P.W.メレディス少佐。兵士たちはルイス軽機関銃2丁と1万発の弾薬を手に、楽観的なムードで臨みました。しかし、その予想はすぐに打ち砕かれます。
- 巧みな回避行動:エミューは機関銃の射程を巧みに保ち、兵士が近づくと瞬時に小さなグループに分裂して逃走。狙いを定めることすら困難でした。
- 待ち伏せ作戦の失敗:ダムの近くで1000羽以上の群れを待ち伏せましたが、いざ射撃という時に機関銃が故障。大半を取り逃がしてしまいます。
- トラックでの追跡劇:トラックに機関銃を積んで追いかけるも、時速50kmで悪路を疾走するエミューに追いつけず、揺れでまともに撃つこともできませんでした。
結果、約2500発の弾薬を消費し、殺害できたのはわずか50羽程度。メレディス少佐は「エミューは戦車のように不死身だ」と、その手強さに舌を巻いたといいます。
第二次作戦:再度の挑戦と「人間の敗北」
農民の再度の要請を受け、軍は11月13日から第二次作戦を開始。今度はいくらかの戦果を挙げたものの、決定的な成果には至りませんでした。
最終的に、作戦は12月10日に打ち切り。公式報告によると、消費弾薬9,860発に対し、確認された殺害数は986羽。エミュー1羽を仕留めるのに平均10発の弾丸を要した計算です。
作戦は事実上の大失敗。国内外のメディアはこれを皮肉たっぷりに報じ、エミュー戦争は「人間が鳥に負けた戦争」として、不名誉な歴史を刻むことになりました。
| 作戦項目 | 第一次作戦 | 第二次作戦(全体) |
| 期間 | 1932年11月2日~8日 | 1932年11月13日~12月10日 |
| 報告殺害数 | 50羽(公式) | 986羽(公式) |
| 使用弾薬数 | 約2,500発 | 9,860発 |
| 殺害効率目安 | 約50発 / 1羽 | 約10発 / 1羽 |
戦いが残したもの:生態系と社会への意外な影響
軍事作戦は失敗に終わりましたが、この出来事はオーストラリア社会と自然環境に様々な影響を残しました。
- 報奨金制度への転換:軍事介入を諦めた政府は、エミューを殺害した者に報奨金を支払う制度を強化。皮肉にも、この方が個体数抑制に「効果的」だったと評価されています。
- エミューの保全状況:大規模な駆除が行われたにもかかわらず、エミューは絶滅することなく、現在、IUCNレッドリストでは「LC(軽度懸念)」に分類されています。
- 国民の意識:この作戦は国費の無駄遣いとして批判を浴び、政府の野生動物管理方針に大きな影響を与えました。そして何より、人間と野生動物の関わり方について、社会的な議論を巻き起こしたのです。
エミュー戦争からの教訓:滑稽な歴史が現代に問うもの
エミュー戦争は、単なる歴史の珍事件ではありません。そこからは、現代に生きる私たちが学ぶべき、多くの重要な教訓が見えてきます。
野生動物管理の難しさと倫理
この戦争が最も明確に示したのは、人間の視点だけで野生動物を「害獣」と断じ、短絡的な解決を図ることの限界です。科学的な生態の理解を欠いた管理策は、非効率なだけでなく、予期せぬ副作用を招きかねません。
現代におけるエミューの価値
かつて軍隊まで投入されたエミューですが、今日ではその価値が見直され、新たな産業資源として注目されています。
- 食肉:低脂肪・高タンパクな健康食材として評価。
- エミューオイル:保湿・抗炎症作用から化粧品や医薬品に活用。
- 生態系の再生:雑草を食べさせることで耕作放棄地を再生する試みも(日本でも実施)。
「害獣」から「保護・管理の対象」、そして「有用な産業資源」へ。エミューに対する人間の価値観は大きく転換しました。
結論:珍事件では終わらない、エミュー戦争の物語
1932年のエミュー戦争は、世界恐慌、国家政策、そしてエミューの生態という、複数の要因が絡み合って発生した、一種の悲喜劇でした。
この出来事は、人間が自然をコントロールしようとする試みがいかに困難で、時には滑稽な結果を招くかを教えてくれます。そして、気候変動や生物多様性の損失といった課題に直面する現代においてこそ、その教訓は重要性を増しています。


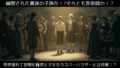
コメント